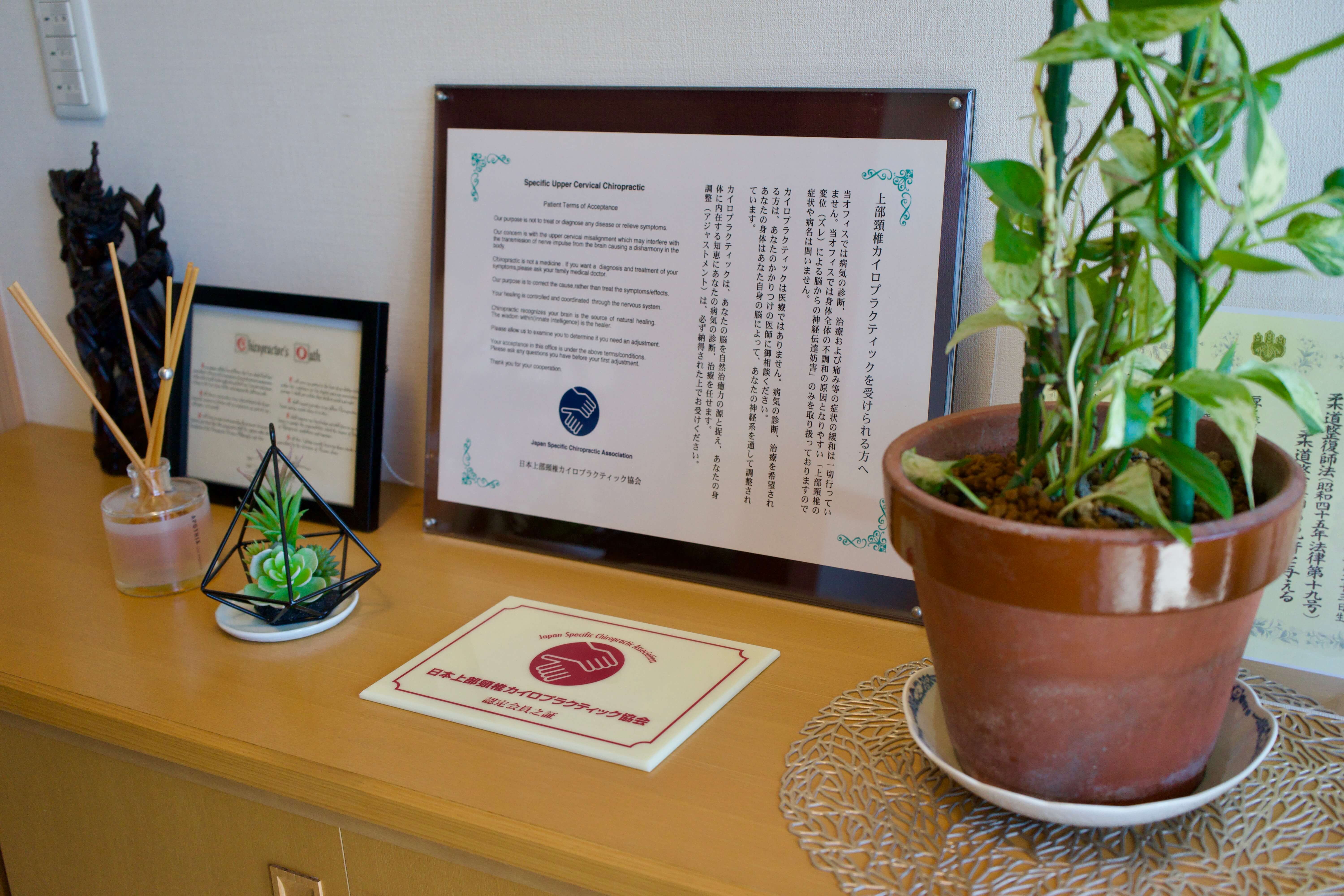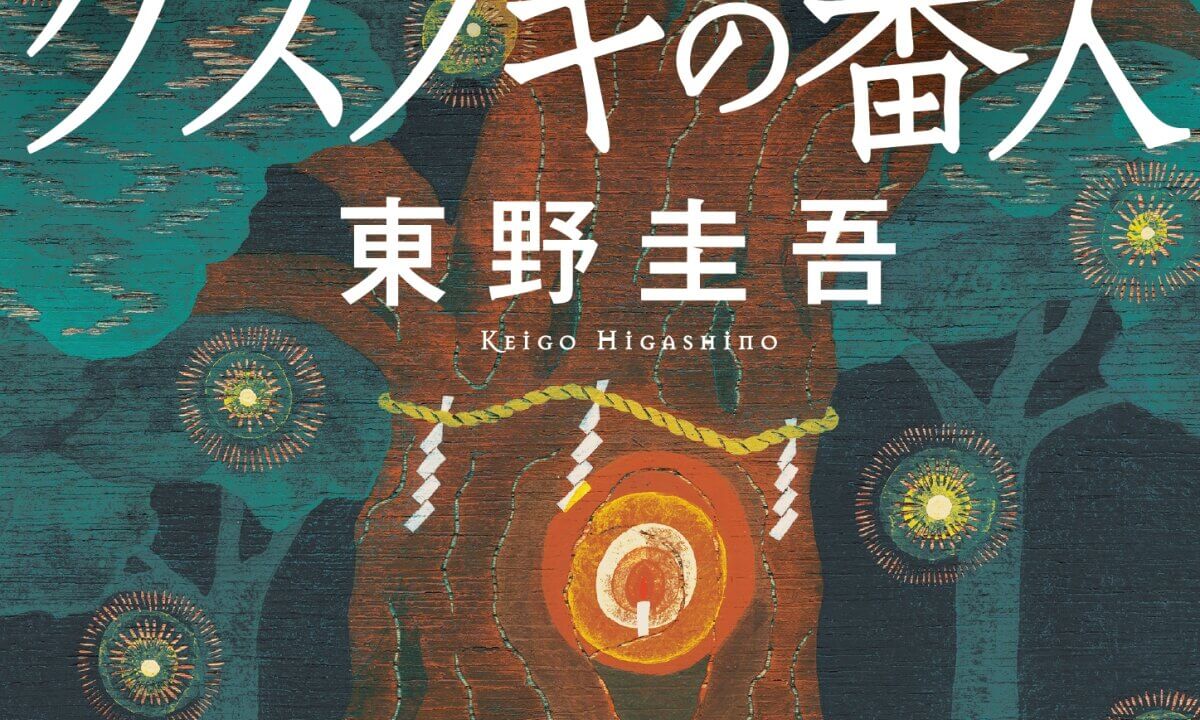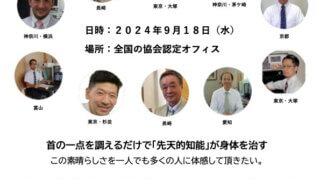最近は本を読む時間を増やしたいとの思いから、今年に入ってから2冊目の小説は人気作家、東野圭吾さんの「くすのきの番人」を読みました。
ざっくり言ってしまうと先日までハマっていたドラマ、「海に眠るダイアモンド」のようなとても見応えのある群像小説でした。(何ならこの脚本を書いた方はこの小説からある程度着想を得たのでは?とも思えるような設定もあったり)血の繋がりや家族の絆といった面からみると、松本清張の「砂の器」なんかにも共通してくるような。クライマックスに至っては、これでもかと伏線回収のオンパレードで休日の朝から号泣ものでした笑
あらすじは不当な解雇によって職を失った若者が、腹いせに元勤め先に盗みに入り窃盗の罪で警察に捕まってしまうところから始まります。身寄りは高齢で、頼りのない祖母しかおらず、途方に暮れていたところ、それまで全く縁のなかった伯母に助けられ、その代わりの条件として、神社にあるくすのきの番人をすることになる、というお話です。そしてそのくすのきには満月と新月が近づいてくると、夜な夜な”祈念”をするために人が訪れる。次第のその番を任された主人公は、そのくすのきが持つ不思議な力の謎を知っていくことになります。
前置きが長くなってしまいましたが、私たちも普段、神社に行ったらお願い事をしますよね。仕事、お金、恋人、健康、あれが欲しいこれが欲しい。とにかく神様お願いします、私にそれをくださいと言った調子で。ちょっと変わってる人だったら、世界を平和にしてくださいって願ってみたり。(私はたまにしてます)
しかしこの物語はちょっと違うんですよね、その辺りが。あまり言ってしまうとネタバレになってしまうので、やめときますが日本の大きな会社には企業理念がありますよね。例えばイオンだったら会長の岡田さんが、「戦後心も体も傷ついた人たちが、買い物をしているときは笑顔になっているのを見て、小売業は平和産業であることを知った」みたいなことです。
話を私たちが、神社に行った時のことに戻します。そういった会社が「儲かりますように」とお願いするのと、先ほど例に出した企業理念って同じようで違いますよね。確かに儲からないと会社は存続してはいけませんが、理念の目的は人々の笑顔ですよね。だから会社が儲かっているだけじゃ、人々は笑顔にならないと言うことです。(鶏が先か卵が先かになってしまいますが。)
最近はスーパーにいても、笑顔で買い物している人ってあまりいないですよね。あらゆるものが値上がりして、日本人の主食のお米も去年の倍ぐらいの値段をつけています。みんなどうしたら家計をやりくりできるのか、とても困っています。戦後貧しい中を生き抜いてきた人々が、明るい未来を夢見て、思いを込めて作られていった今の日本は、一体どこへ向かっていっているのでしょうか?またこれから先、私たちは次の世代へどんな思いを残すことができるのでしょうか?
その答えは、くすのきだけが知っているのかもしれません。